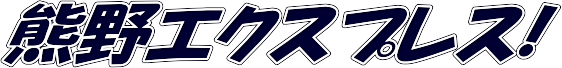森本剛史の世界紀行~⑨神に捧げられた、極彩色の芸能島 バリ島
「祝祭と芸能」のバリ島。島に一歩足を踏み入れた途端、祝祭の渦に巻き込まれてしまいそうだ。世界に類を見ない圧倒的な芸術性と卓越した世界観。そこには芸能を通じ無数の神々と交信する人々がいる。
2002年の爆破テロは、どこの国の人より平和を祈るバリの人々にショックを与えた。バリ人ほど世界平和を祈念している人たちはいないだろう。祈りのバイブレーションが熱帯の空気の中に響いている。観光客も戻り始めているようだ。
■神々への「供物」としての芸能■
寺院の割れ門の上には大きな入道雲が沸き立っている。青空に伸びた椰子が風に揺れ、むせ返るような熱帯の香りが充満している。風に運ばれて細い通りの向こうからガムランの音が聞こえてきた。正装した男女の長い列がしずしずと寺院に向かってくる。女性たちの頭上に積み上げられた、20キロもの供物の果物が鮮やかだ。
やがて一行は寺院に入り、奉納の踊りと音楽を始めた。ガムランの金属音が空気を震わせ、うねり、寺院の中に強力な磁場を形成していく。振動に包まれていると陶酔感が込み上げてきて、「祝祭と芸能の島」を実感する一瞬である。
初めてバリを訪れた人にも必ずこのような遭遇があるといっても過言ではない。それは島内に大小合わせて2万ものバリ・ヒンズーの寺院が存在し、1年中どこかの寺院で祭が行われているからだ。イスラム教国であるインドネシアで、バリ島は唯一ヒンズー教が勢力を持つ島である。だが単なるヒンズー教ではない。バリ特有のアニミズム(自然崇拝)と結びついた独特のヒンズー教なのである。
この島では日常生活と祭との明確な境界線はない。日常が祭で、祭が日常と言っていいだろう。バリの人々にとって生から死まで祝祭の連続なのだが、その中心となるのが芸能である。敬虔な彼らは、朝に夕に神々に祈り、野良仕事の後は芸術家に変貌する。ある者はガムラン奏者に、またある者はバロンダンスなどの踊り子として。
彼らを見て私が連想したのは宮沢賢治のことだった。賢治が岩手の農民に望んだのは、日中泥まみれになって働き夜に芸術家に変身するバリの農民だったのではないか。バリ島が最初に世界的にブームになったのは1930年代。賢治の耳にもバリの農民像は伝わっていたはずである。
バリの音楽はこれらの神々に捧げる「供物」として発達してきた。ここでは宗教と音楽、そして踊りとが強固に結びついているのである。バリという地名からして、古代ジャワ語で「神に捧げられた供物」を意味するという。バリの芸能は鑑賞のためにあるのではなく、どれも神話や宗教と深く結びつき、神々や先祖の霊と交信するために存在しているのだ。
ウブドに住む踊り手、イマデ・マハルディカさんに話を聞いた。彼はバロンダンスの若手のホープで、獅子舞に似たバロンの中に入って踊る人だ。笑顔に白い歯が印象的である。
「私にとって、踊るということは特別なことではなく、空気を吸うとか水を飲むとかと同じくらい当たり前のことです。神様への奉納として踊ります。自分も観客も神様も幸せになれるのだから、これほど素晴らしいことはないですね。タスクがなければいい踊りには決してなりません」。
タスクとは「魂」とか「精霊」とか訳せるが、バリの芸能のキーワードである。芸能はバリ人と神々とをつなぐ媒体と考えていいだろう。音楽もダンスも個人の表現ではなく、バリという島の日常性の表現として存在しているのだ。
■色が踊る、パワフルなバリ絵画■
バリに行くと一度は目にするバリ絵画。ジャングルの中に跋扈する魑魅魍魎を描いたのがあるかと思えば、「ラーマヤナ物語」の絵解きもあるし、まるで日本画のような鳥や植物の絵もある。
バリ絵画はどれもパワフルだ。額縁の中に納まりきらない躍動感に満ちあふれている。空白恐怖症とでも言うべき精緻な描き込み。雷が鳴り稲妻が走ると、それぞれの登場人物が今にも動きだすかのような気がした。
バリの絵はもともと寺院や宮殿で使われる目的のために描かれた。神話や伝説、インドの一大叙事詩「ラーマヤナ」などに素材を取った作風は、ワヤン・クリッ(影絵芝居)の影響を強く受け、登場人物はすべて影絵のように平面的で遠近感がない手法で描かれた。これはカマサン・スタイルと呼ばれ、使用できる色の数も限られていた。
ところがバリ島にひとりの画家がやって来たことから、バリ絵画は新しい地平に向かって第一歩を踏み出すのである。その画家の名はヴァルター・シュピース。アンリー・ルソーに強く影響されたドイツ人画家で、ドイツで興った新即物主義のメンバーであった。
1925年に初めてバリを訪れたシュピースはこれまでに体験したことのない自然、文化に魅了されてしまう。もちろんバリ絵画にも。彼はバリの画家たちに絵具を与え、紙やキャンバスに絵を描くことを教え、遠近法や陰翳のテクニック、宗教的なテーマ以外にもいくつものモチーフがあることを示唆した。若きバリの画家たちは、のびやかで解放感あふれる日常生活や自然を遠近法を使い、鮮やかな色を使って表現するようになった。
1936年に、シュピースはバリの芸術や文化を振興させるために、バリ滞在のオランダ人画家ルドルフ・ボネの協力を得て、「ピタ・マハ画家協会」を設立する。シュピースは絵画のみならず舞踊、音楽、写真の分野でもバリの文化発展に貢献し、バリの国際化に努めた。その結果として、西欧人がイメージする「南国の楽園バリ」が創造されたのである。だから、現在私たちが見るバリの芸術や芸能は、1930年以降のバリと西欧との遭遇の結果生まれたものだということを知っておくべきだろう。まさに彼はバリのルネッサンスの仕掛け人だったのだ
これらの先人たちの努力が、今実を結んでいるのである。バリの画家たちの作品はウブドにあるプリ・ルキサン美術館、アグン・ライ美術館(アルマ)、ネカ美術館などで見ることができる。
ウブドの帰り、望遠レンズでのぞいた椰子の密林は遠近感がなく、葉が重なって見えた。スコールの後の湿気をいっぱい吸い込んだジャングル。気が谷間にあふれている。ファインダーの中の風景は、まさに1枚のバリ絵画だった。
■音の格闘、竹管爆奏■
デンパサールから約80キロ、ジャワ島が見えるバリ西部に位置するヌガラには、ジェゴグと呼ばれる重低音の竹のガムランがある。ヌガラ周辺に生える7種類の竹だけを使った楽器演奏なのだが、ムバルンという2つのグループが競演するという演奏形態がすごい。相手の演奏を壊すように邪魔をしながら演奏するというスタイルだ。いろんな国の音楽を聞いたが、鳥肌が立った民族音楽はこのジェゴグが初めてだ。
この楽器は8本の竹で構成された単純な構造で、木琴のように竹を打ち鳴らす。15人が1チームで楽器の数は14台。最も低音の楽器のいちばん大きな竹は長さ3メートル30センチ(直径18センチ)もあった。
私たちが聞いたのはスアール・アグン芸術団のサンカラ・アグン村チーム対プンダム村チームの音のバトルだった。前者は青い民族衣装なので青組、後者は黄色の衣装なので黄組と便宜的に呼んでおこう。スアル・アグンもリーダーのスウェントラさんはこう語る。
「演奏する場所、時間帯、空気の流れによって微妙に音が違います。太陽が沈んだ後がベスト。いちばんいい演奏場所はこのヌガラです。ここで聞くジュゴクには目に見えないタスクが宿っていますから」。気温26度、湿度40%の時が最適の環境らしい。
両チームがそれぞれ神への祈りの音楽「トゥルトゥガン」や「神への報告」を演奏した後、青組が演奏を始めた。気持ちよい竹の響きがまわりを包む。人間の脈拍と同じような心地よいスピードだ。淡麗であり豪奢である。20分の演奏の後、攻撃してこい、というリーダーの合図に、待機していた黄組が演奏に加わった。
今までの青組の音を聞いて、今日はどういう攻めかたでいくか十二分に対策を練ったに違いない。青組のトッキリ、トッキリという規則的な音に、黄組がセンカ、センカ、ワッセワッセ、ダンダン、トッキリと仕掛けていく。相手の音を消しながら自分たちの強力な音を載せていくのだ。
挑発と撹乱。段々ペースが速くなってくる。お尻にズンズンと響いてきて爆音が背骨を駆け上がる感じだ。手に持っているコップの水が振動で揺れているのがわかった。鳴いていた蝉があまりのパワーに恐れたのか急に鳴きやんでしまった。
複雑であり単純、単純であり複雑。たった4つの音階で構成されているにもかかわらず、音が波立ち、うねり、強力な磁場を形成していく。音が凛とした端正さで私を包み、私のまわりで渦を巻きながらどんどん加速していく。演奏者たちは機械のように正確に楽器を叩く一方で、目はうつろに中空を見すえ、体を揺すり、時々ヤッーとか気勢をあげる。重低音がチェロのようにも聞こえるし、男性コーラスのようにも、あるいは津軽三味線のようにも聞こえる。
両チームの竹管から叩きだされた青、黄色の゛おたまじゃくし″が空中で入り乱れ、お互いもつれ合い、格闘をおっ始めている。これは音のバトルだ、格闘技だ、プロレスだ、と思わず叫びそうになった。青組のリーダーは「どうだまいったか」という一瞥を黄組に向ける。「なんの、なんの」。ますますバトルは激しくなり、エネルギーに満ちた音は天空の彼方に飛び出していくように思えた。