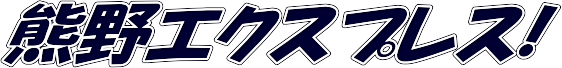森本剛史君との思い出~⑨シンガポール2・炒飯編
剛やんと久しぶりにシンガポールで再会して以降も、家内の弟家族や長女の幼稚園のときの先生など様々な友人たちが来星してくれました。国内にいてもなかなか会えない人たちにも、外国にいるからこそ会えるということもあったと思います。
ある日、剛やんから、待望の一冊が届きました。彼がシンガポールで取材し、私がわずかながらも協力したあの一冊「海外食べあるき・ショッピング シンガポール」(1988年10月初版発行・昭文社)でした。
見ると、あの「幻の炒飯」は、どの高級レンストランよりも、どの一流ホテルよりも大きく、見開き2ページに亘って紹介されていました。やるな!剛やん。やっぱり感性は一緒やった!うれしかった!おまけに、あいつ、協力者として、私の名前まで巻末に紹介してくれていました。
でもこの本はもう、書店で見ることはありませんので、「幻の炒飯」のページのみ紹介したいと思います。
◇究極の炒飯ここにあり◇シンガポールに住んでいる日本人の間でつとに有名な幻の炒飯に遭遇することができた。 店の入り口左に炭火のかまどがあり、ここが調理場。痩せたおばさんが煙のなかで大きな中華鍋を握っていた。彼女の細腕の右の力こぶだけは小さなお餅をのっけたように盛り上がっている。鍋から空中に放り投げられた飯が炎と交差する時、ジャッと音が出た。香ばしい匂いが店内に漂う。 おばさんは米の一粒一粒がくっつかないように、しかも米の一粒一粒に卵がまんべんなく絡むように力を込めて鍋をかきまわし、飯を宙に舞い上げる。まるで、炎と決闘しているようだ。声をかけたが、口も利きいてくれない。注文は別のおばさんがとりに来た。 9卓の丸テーブルは全部ふさがり、お客は黙って待っている。その上をふたつの扇風機がゆっくり回っている。奥には神棚があり、その下には油でテカテカ光っているオレンジ色の電話機。隣の食器棚のガラス戸には12枚の茶色に変色したサッカーチームの絵葉書が貼ってあった。 30分たって、大きな皿に盛った3人前の炒飯ができ上がった。カニ肉をはじめとしてシーフードもたっぷりと入っている。口に入れてみると、ふわふわでしかもパラッとしている。口一杯にカニ肉のいい香りが広がった。実に気品のある、この逸品だった。 この店の名前は「榕光」(YONG KUANG)。チャイナタウンを横切るサウス・ブリッジ・ロードからネイル・ロードに入ってカントンメント・ロードの1本手前を右に入ったところにある。左斜め前が広東料理で有名な「マジェスティック・レストラン」だ。 ちなみにこの炒飯のお値段、1人前で10Sドル(標準の3倍)、3人前だと25Sドル。シンガポールで料金が一番高い究極の炒飯である。 「榕光」(YONG KUANG) (文:ライター・伊藤ユキ子さん) |