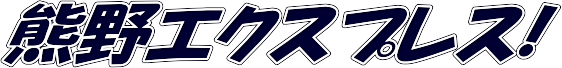森本剛史君との思い出~⑧名古屋・シンガポール1・取材編
名古屋での生活
家内は母親の看病で実家の京都、娘は新宮、そして私自身は名古屋で一人暮らしと、家族三人が別々に暮らし始めて1年が慌ただしく過ぎていきました。少し緊張しながら名古屋支店で配属された課では私が最年少でしたが、上司、先輩たちは全員とても暖かく迎えてくれました。この時ほど人の心の暖かさを強く感じたことはなく、一生忘れることができません。
このころよく世間では、「名古屋というところは、東京と大阪の狭間で閉鎖的なところで、ここで商売を成功させるのは至難の業だ」ということが言われていました。私は、ある意味で開き直りもあったので、この地でとことん溶け込んで思いっきり仕事をしてやろうと意気込んでいたのですが、余分なことを考える必要もなく、同僚にも顧客にも恵まれて自然と溶け込むことができました。
少し環境も好転し、一家三人が一緒に過ごせるようになって暫くしたころ、課長から呼び出され、シンガポール転勤を告げられました。当時わが社では、世界の駐在地のベスト3は「3S」だと言われていました。Sydney, San Francisco, Singapore の3つのSです。たしかに、治安、気候、医療、教育など駐在員家族が生活するうえで心配の少ない環境に恵まれているところでした。
名古屋での仕事が順調に伸びたのと、駐在資格もすべてクリアーしていたのでスムーズにことが運びました。家族全員でいろいろと苦しみながらも何とか乗り越えてきた甲斐があった、やっと将来への不安が薄らいできたという感じがありました。ただひとつ、義母の闘病が依然として続いていることが心残りでしたが。
ところが、駐在の話を家内に告げると、一緒に行きたくないといい出したのです。振り返ると名古屋での生活は、毎晩のように12時過ぎの帰宅、土曜日はゴルフ、日曜日はぐったり疲れて昼寝という始末でした。その頃には次女もいましたが、二人の娘と遊んでやるとかお風呂に入れてやるとかの優しさを忘れていました。家内はあまり言わなかったので気持ちに気づいていませんでした。
「国内にいてもこんなに忙しい毎日なのに、海外駐在になったら益々忙しくなり、家庭が壊れてしまう」というのが家内の思いでした。じっくり考えてみると、確かに私は、仕事の忙しさにかこつけて家族を包み込むことを忘れていました。反省してこの生活を切り替える意味でも一所生懸命説得した結果、何とか納得してくれ一緒に行ってくれることになりました。
シンガポールでの再会
家族同伴で無事赴任できて2年少し経ち、新しい外国生活にも慣れた頃、剛やんから連絡が入りました。旅行雑誌の取材でシンガポール出張が決まったので、現地事情の提供に是非協力してほしいというものでした。彼と再会できると思うと、数年前人生の波乱に巻き込まれたこともあって忘れかけていた友のこと、故郷の情景がつぎつぎと浮かんできました。
取材班は、カメラマンの馬渡さん、ライターの伊藤さん、リーダーの剛やんの3名のチームでした。今回の彼らの仕事は、地図で有名な昭文社の海外旅行ハンドブック「海外食べあるき・ショッピング」シリーズのシンガポール編を担当するものでした。その時まで、①ハワイ、②香港、③台湾、④韓国と刊行済みでシリーズ5番目となるということでした。この種のガイドブックは履いて捨てるほど溢れているので、何か他誌にはない特徴を持たせたいと意気込んでの来星でした。
実は、彼から連絡があったときから一つの腹案を持っていました。彼とは、蓬莱小学校1年5組からの長いつきあいなので、何を求めているかは手を取るようにわかりましたので、とっておきのネタを提供するつもりでいました。どんなガイドブックでも外す訳にはいかないグルメスポットやレストランを回った後、そこに連れていきました。
 チャイナタウンの一角におばちゃんが腕を振るって評判をとっている小さな食堂がありました。そこで提供される炒飯が、当時、日本人居住者の間で話題になっていて、それは「幻の炒飯」と呼ばれていました。このことについては別の記事でも紹介していますが、とにかく蟹がいっぱい入っていて他では味わえない豊かさを感じることのできる大好きな味でした。
チャイナタウンの一角におばちゃんが腕を振るって評判をとっている小さな食堂がありました。そこで提供される炒飯が、当時、日本人居住者の間で話題になっていて、それは「幻の炒飯」と呼ばれていました。このことについては別の記事でも紹介していますが、とにかく蟹がいっぱい入っていて他では味わえない豊かさを感じることのできる大好きな味でした。
値段は、通常の3倍(S$10)するので、後でもめることを避けるためでしょう、おばちゃんが、10ドルだけどいいんだね?と必ず確認してから作り始めるのが印象的でした。
当時の私の仕事は、何でもいいからこの支店で受け持った課で一人食べていけるようにすることが課題でしたので、とにかく東南アジアを歩き廻っていました。とりわけ、シンガポール国内のレストランやホテルを回り、食品原料の流れなどを調査することも仕事の一貫として必要なことでした。
あちこちのレストランとも親しくしており取材にも協力的でしたので、時間の許す限りできるだけ沢山のところに連れて回りました。でも、チームが最も気にいったのは「幻の炒飯」で、この本の目玉にできるととても喜んでくれました。私としても「してやったり」で小さい頃から「ウマが合う」と言われてきた、剛やんと私の感性がぴったり一致したということの証明でした。
取材が一段落したころ、このチームに自宅に来てもらい食事を楽しみました。家内も、剛やんが2度目の世界一周旅行直前に大阪で会って以来の再会でした。私が家内に新宮の話をするときは、いつでも剛やんが登場したし、家内も、もう剛やんのことはよく分かっていたのでお互い遠慮も無用で話ができました。二人の新客からも最近の日本の状況などを聞きながら楽しい一夜が更けていきました。