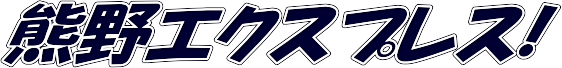谷中安規「画人としての半生」
| 旬日ならずして、風の如く、当時、新築の佐藤春夫氏方にまかりいでぬ。君のくるのを待ってゐたと申されき、「苦楽」と云ふ雑誌に支那小説をかくが挿絵をかきては如何に、約一年程、連続す、さすれば君の生活も助からう、われ未熟乍ら人のなす事、おのれに出来ぬ事なしとの性質なれば、承引なしぬ。
四五日して、いよよきまりぬ。その日夜ふけて、高橋新吉と同居せばいかにとの話、前日あひたれば、先生よりたのみをかれしと見え、高橋君の名刺渡されぬ。さき程高橋きたり、不在にてもさしつかへなきやう、この名刺にかきそえたれば、下宿のおかみに出せばよろしい、あがって、勝手に床をしいてねてをれと、云ひのこしてかへりゆきしよしなりき。 されば、戸塚なる下宿屋におもむき、下宿のおかみに名刺を示せど、ケンもホロロに追いかへされぬ。せん方なし、終電もとくにすぎたれば、浅草なるキチン宿へもかへれず、困じはてて、佐藤邸の木戸をたたける時は深更けなりき。佐藤氏、自ら出て来られぬ。二階の間にふしねど云へど、先生と床をならぶる事心ぐるし、さらばと、先生自ら暖炉に点火し、これを引きねなどいひて、ふとんなどもちだしこられぬ。高橋氏の下宿へは改めて翌日ゆきぬ。 |
『版芸術』第8号(昭和7年11月)より
(谷中安規が佐藤春夫に初めて会った頃)