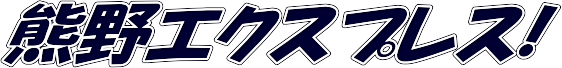館長のつぶやき〜「佐藤春夫の少年時代」73
「愚者の死」の製作 (続)
愚者の死」が、この年「スバル」の3月号に発表されたとき、いま一般に普及しているような、「うべさかしかる商人の町は歎かん」と「ー町人は慎めよ」との間の行空(ぎょうあ)きはありません。ひとつの纏(まと)まりとして聯(蓮・れん)を形づくっている。そうすると、文脈のうえでは、「聞く」ということばは、直接は「恐懼(きょうく)せりと」を受けているのですが、「更にまた説けよ」までを含めて考えてみることをも可能にします。
「商人の町」新宮町の「恐懼」の模様は、東京在住であった春夫の耳に、どのような形で伝わっていったのか。それは、当時の新聞を幾つか読むことによって、ほぼ推測できます。春夫は、「教師らは国の歴史を更にまた説」くことも、地方新聞の記事を通して知ったのです。
例えば、2年前の1909年(明治42)秋、新宮中学でストライキが勃発したとき、第4回卒業の下里出身の松本実三は第1高等学校に在学中でしたが、このストライキの発端となった「新宮中学の怪聞」の記事を、約1週間遅れで読んでいます。それは、紀州田辺で刷られていた「牟婁新報」に掲載されたものですが、新宮中学ストライキの報は東京の「万朝報(よろづちょうほう)」にも載り、遊学の身を苛立(いらだ)たせているのです。
その「牟婁新報」が、この年1月24日付に「新宮町民の恐懼」と題した記事を載せています。そこに、「大逆事件に新宮町より三名迄大罪人を出したるは至尊に対し恐懼に堪へず且同町の一大不面目たるを以て十九日役場の議員及び区長等会合し協議の結果二十一日午後一時より新玉座にて町民大会を開き謹慎の誠意を表し新宮中学校教諭は我が国体及び歴史に就き講演を為せり」と述べられています。他の中央新聞にも似たような記事が出ています。それらを読み比べてみると、町民大会はやはり時節がら好ましくないとのことで開かれず、「新宮中学教諭」が講演を成した形跡も見当たりません。春夫も、東京で「牟婁新報」などの記事を直接眼にしていたのではないかと思われます。これらの新聞記事を題材にして「愚者の死」は書かれたのです。この頃の牟婁新報紙は、かつて荒畑寒村や管野スガらが筆鋒を振るった頃の覇気や精彩は、もうない。ただ東京では、所定の場所で、1週間遅れぐらいで閲覧できたようです。「愚者の死」は、これらの記事に拠(よ)りかかり過ぎているといえなくもない。反語説に拠りながらも、そうして春夫のこの頃の他の作品、例えば門司駅で天皇のお召し列車脱線事故の責任を取って自裁した駅長を悼む詩、「清水正次郎を悼む長歌並短歌」などにもその一端が窺えるのですけれども、「愚者の死」について限ってみれば、与謝野寛の「春日雑詠(はるひざつえい)」と読み比べてみて、やはり「反語」ということばを用いてみれば、その徹底性という面では劣るのはやむをえない気もします。
1911年(明治44)4月の「三田文学」に発表された「春日雑詠」は、1915年(大正4)に刊行された寛の詩集『鴉と雨』に収録される際に、「誠之助の死」とタイトルされて、最初の発表時の後半部分が独立させられた。その編集は、妻の晶子によってなされたと私は確信しています。(その詳細は「熊野誌」58号所収の「与謝野寛の詩「誠之助の死」成立にみる、晶子の「大逆事件」」を参照していただきたい。)
「誠之助の死」が、「大石誠之助は死にました。/いい気味な。」と、やや唐突に始まる印象を与えるのも、そういった事情からですが、「春日雑詠」の「いつに無い、今年二月の暖かさ」のなかで「心憎い春の小鳥のすさび」に苛立っている心象がそのまま、友人の刑死に対するどうしようもない憤怒(ふんぬ)へとつながり、しかも反語表現の徹底さで無念の気持ちが増長されてゆく、その意味で前半の序曲としての効果は無視できないように思われます。反語表現の徹底という点で述べれば、「愚者の死」をはるかに凌いでいるとも言えます。この時点での、与謝野寛と春夫の年輪の差や文学的経験の差と言うものが現れているとでも言えましょうか。
発表時期がほとんど同時なのですが、お互いの影響関係はまったく無かったのです。比較するならば、「愚者の死」と「春日雑詠」とを比較すべきなので、そこに新しいタイトルの「誠之助の死」を割り込ませるのは、作品成立の事情を全く無視することになるのです。
寛の「誠之助の死」が独立するとき、一部字句、ルビ、行間などが訂正されていますが、ひとつ大きなことは、「例へばTOLSTOI(トルストイ)が歿(し)んだので、/世界に危険の断えたよに。」の箇所が削除されていることです。誠之助の「危険思想」になぞらえられた明治末期のトルストイの受容が、大正時代に入って、武者小路実篤らの白樺派などによって人道主義者として見直されるという潮流の中で、「危険」思想家としての側面が薄められていった、わが国でのトルストイの受容史をふと垣間見させてくれてもいます。晶子は、春夫と同行した新宮行を決行した後、夫の詩集『鴉と雨』を編纂して、後半部を独立させて「誠之助の死」とタイトルを付したのです。烏と雨とは、まさに熊野の地の象徴でもあり、晶子が実際に体験したことだったのです。当然、先行作品の春夫の「愚者の死」も考慮したでしょう。「愚者」を「誠之助」と読み替えたタイトルを、晶子に思いつかせたのかも知れません。おそらくそういうことも話しながらの熊野への長い船旅であったに違いありません。
ところで、「愚者の死」発表の翌月4月号の「スバル」には、「街上夜曲(がいじょうやきょく)」と題して、新詩社同人数名が12編の詩を競作しています。新宮出身で「スバル」の編集にも関与した和貝夕潮のものは、次のようなものです。
「×
電車が通れば、/自働車が走れば、/豆売が歌へば、/夕刊売が叫べば、/瓦斯会社の白壁を、/右についてまはつた格子戸のうすくらがりから、/夢でも見たやうに、/発狂でもしたやうに、/時ならぬカナリヤが/あの洋妾(らしゃめん)の唄をうたひだす。(彦太)」
それらのうちで、春夫の作品がもっとも際だったものになっていて、この1編の方こそが、電車待ちの場面にはむしろ相応(ふさわ)しいし、その衝撃の余韻が直に伝わってくるものになっています。
「×
号外のベルやかましく/電燈の下のマントの二人づれ、/ー十二人とも殺されたね。/ーうん……深川にしようか浅草にしようか。
浅草ゆきがまんゐんと赤い札。/電車線路をよこぎる女の急ぎ足。(春夫)」
まったく普段とは変わらない庶民の生活様態が活写されるなかで、「十二人殺された」のセリフが突出しています。壮絶なほどの余韻が、「大逆事件」の理不尽さをもののみごとに浮かび上がらせています。まさに権力の大きな力によって「十二人とも殺された」のでした。
そんなわけで、「誠之助の死」の成立事情を考えれば、当初はあくまでも「春日雑詠」だったのであり、序曲の部分は無視できないものがあるのです。「愚者の死」と「誠之助の死」とを並び論ずることも、やや無理が生じることになるのです。
春夫の「反骨精神」は、春夫に強力な「個」の自覚を促し、抗(あらが)いの態度は、反骨の精神として、少年時代、故郷に容れられぬところから生まれて来たとも言えます。「個」の力が「全体」や「国家」に収斂(しゅうれん)されざるを得なかったとき、そこには「日本人ならざる」態度や「愚者」が、現れざるをえない。自身の立ち位置を春夫は要請されてきていたとも言えます。長々と述べてきた拙ない文章も、いよいよフィナーレへの曲が始まります。
辻本雄一