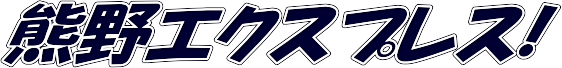館長のつぶやき〜「佐藤春夫の少年時代」72
「愚者の死」の製作
「千九百十一年一月二十三日/大石誠之助は殺されたり」で、「愚者の死」は始まる。
雑誌「スバル」の、1911年(明治44)3月号に発表されたこの詩は、一般に思想的な意味合いを帯びたものとして、「傾向詩」と呼ばれていますが、春夫は後の詩集にこれらを採りませんでした。だから、広く一般読者の目に触れるのは、戦後になってからのことです。
「明治四十四年」ではなく、「千九百十一年」と西暦表記した所には、意図的なもの、作者佐藤春夫の精神的な位相を読み取ることができます。そう考えれば、「一月二十三日」も単なる誤記ではなく、『革命伝説』(神崎清著)での記述のように、抗議の意味を蔵しながら、事実をわざとズラせて詩的な仮装をねらったとする観方もうなずけます。
さらに、「愚者の死」は次のように続きます。
「 げに厳粛なる多数者の規約を/ 裏切る者は殺さるべきかな。
死を賭して遊戯を思ひ、/民俗の歴史を知らず、/日本人ならざる者/愚なる者は殺されたり。
「偽より出でし真実(まこと)なり」と/絞首台上の一語その愚を極(きは)む。」
春夫は知己である誠之助を、「多数者の規約を裏切る者」と規定しています。天皇暗殺という「遊戯」に係わった「愚者」と呼ぶとき、そこには自分自身を断罪するかのような強さが感じ取れます。「愚者」の像には春夫自身の残影が付き纏(まと)ってみえます。
「愚者」はまた、「日本人ならざる者」でもあったがゆえに映る姿でもあるのです。「多数者の規約」に縛られる「日本人」、それが国家に忠実な日本人の理想像であるはずだとするのです。国家への裏切り、反逆を許すまじの強い力が、「愚者」を「日本人ならざる者」を「殺す」のです。
「愚者の死」では、「愚者」や「日本人ならざる者」への、自己の残影を無理に振り捨てるように、後半の「恐懼」の町叙述へと筆致が移ってゆきます。町全体が恐れおののいているという描写は、詩全体の流れから言えば、ひとつの大きな転調を強いてゆきます。
「われの郷里は紀州新宮」と、春夫は自己の出自を述べ、「渠(かれ)の郷里もわれの町」と、大石誠之助への「連帯」感を訴えます。紀州新宮の閉ざされた地勢が、ひとつの空間として浮き上がる仕組みと言えます。しかし、これを「連帯」ととるか否かは、前半の反語的口調の軽重にも係わる難しい問題を含んでいます。ただ、森長英三郎が『禄亭大石誠之助』(1977年・岩波書店)のなかで指摘した「反語のひとかけらも感じられない」とする説は、あまりにも辛(から)すぎる。春夫への嫌悪が先走り、戦後指弾された、春夫の「戦争協力」の残像が色濃く出ているように見えます。春夫のいわゆる「戦争詩」などの問題は、別途考えねばならない重要な問題ですが、それが先行作品の「愚者の死」まで及んでくるのはやや違う気がします。
春夫の反語説への異議は、最近でもひとつの話題になりました。
2017年いわゆる「共謀罪」なるものが多くの反対の声を無視して強行採決されました。その際に「大波小波」欄が「百年ほど前」のことと関連させて、「これで「愚者の死」は増えるだろう」としたのです。そこで引用されたのが、春夫の「愚者の死」と与謝野寛の「誠之助の死」でした。そのことに関して評論家の佐高信がこれらの詩を「低レベルな詩」と切り捨て、明治政府の「お先棒をかつがなかった」人として徳富蘆花を対置して「屈しなかった人」として評価したのです(「週刊金曜日」2017年6月23日号)。そうして自分は森長説に賛同するとしました。図式化することによって、二項対立を作り上げるのは佐高式のようにも見え、切っ先の鋭さは感心するのですが、かなり荒い論であることは否定しようがない。すでに述べたように、若い春夫は蘆花の弁舌にも心酔していたのでしたし、これから述べるように、春夫の作品と寛の作品も必ずしも一様ではない。2つの作品を一からげにすることによって、見えなくなってしまう部分もあるのです。
ただ、佐高が「反語的表現の危険性」を指摘しているのは興味をそそられるます。フォーク歌手の高田渡(わたる)の「自衛隊に入ろう」という歌を聴いて、ある自衛隊から公演依頼が舞いこんだのだと言います。ちなみに高田渡の父高田豊(ゆたか)の詩の才能を評価したのは春夫、春夫は「新人発掘」の名人でした。20歳の青年の前途を祝福する内容で、自身の青年時代への苦い味を重ね合わせながら、「「青年時代は不愉快だ」と看破したのは、たしかにニイチエだ(略)。これは僕の身にもおぼえのあることである。/僕が高田豊の詩に賛成する所以のものは、高田が彼の詩で青年時代といふものがいかに不愉快であるか、その心持をよく描出してゐるからである」と述べ、「高田豊を紹介す」の1文を草しているのです(1925年12月の「読売新聞」掲載、『退屈読本』収録)。その後、高田豊は春夫とは疎遠になり、詩の道からも遠ざかり、貧困の道を余儀なくされます。詩の道は息子高田渡に受け継がれる。父の反骨の姿を見て育った渡は、フォークソング界の旗手となります。「自衛隊に入ろう」は、むしろ反語の反戦歌だったのです。山之口獏(ばく)の多くの詩にも曲をつけていますが、獏も父豊と同世代、春夫が高く評価した詩人のひとりでした。
「反語」であるか、そうでないかを議論するのは、それ自体あまり深い意味を持たないような気もします。
先に「若き鷲の子」の詩の詳細な分析で紹介した山中千春の『佐藤春夫と大逆事件』によれば、春夫のいわゆる傾向詩群にみる春夫の、「反語性」を超えるものとしての、「巧妙なレトリック」は、春夫の創作方法の根本的な態度として位置づけられています。これまでの「傾向詩」と言われるものが、とかく思想、思念の方向からのみ捉えられがちであったことに対して、一石を投じる役割をはたしています。それは春夫を、簡単に「詩人」として片づけられない複雑さを炙(あぶ)りだしているとも言えます。
「日本人ならざる」という、大石誠之助への共感、それは春夫自身の内部にも通ずるという認識は、後の「日本人脱却論の序論」から遡及させて、作品「愚者の死」の解釈に反映させ、「日本人ならざる」という意識が、その時代にあっても、あるいはその時代だからこそ、狭いナショナリズムの枠を超えて、現代にまでつながる日本人の精神性の問題として摘出して見せてくれているとも言えます。それは決して誠之助を冷たく切り捨てているのではない。「愚者」は「日本人ならざる者」であるがゆえに、他者の眼には写る姿なのだということです。とかく日露戦争後、「日本人」というものが国家の枠組みの中に囲い込まれてくる中で、「日本人ならざる者」の位置を保つことには、強い個の自覚が要請されるはずで、時に強い権力の魔の手が及んでくることもあったのです。そうして「日本人ならざる」とする世間の批判の眼を逆手に取って、それだからこそ「日本人ならざる」ことが、普遍性へと繋がる道筋を付けてくれていて尊いのだということを強調している、そんな「読み」を可能にしてくれています。
「愚者の死」に関しては、春夫の同時期の他の作品や、さらに他人の作品と比較検討することによって、作者の真意や、述べようとする意図なりが浮かび出てくるような気もするし、作品としての「弱点」も窺い知れる気がします。そういう意味では、「愚者の死」は、閉ざされた地勢への春夫自身の「係わり」を測る尺度ともなりうるし、大石への「同情」なり何なりが、削(そ)がれてゆく気配を感じさせ、「新宮町の恐懼」へと転化されることによって、春夫自身の強い個の自覚が、さてどうなのかが問われる結果にもなるのです。
「 聞く、渠(かれ)が郷里にして、わが郷里なる/紀州新宮の町は恐懼(きょうく)せりと。/うべさかしかる商人(あきうど)の町は歎かん、
―町人は慎めよ。/教師らは国の歴史を更にまた説けよ。」
辻本雄一