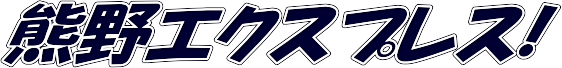館長のつぶやき〜「佐藤春夫の少年時代」71
神田須田町の停車場
東京神田須田町の電車停留所の人ごみのなかで、3人の青年が電車待ちをしていました。3人とも、1910年(明治43)3月新宮中学を卒業した同級生で、上京10ケ月足らず、多少酒が回った様子でした。ひとりは、慶応大学予科に入学して5ケ月ばかりの佐藤春夫です。時は、1911年(明治44)1月18日宵であろうか。東京市電の発足は、この年8月ですから、このときはまだ東京鉄道株式会社経営になる私鉄の路面電車で、市電全盛の時代を迎える矢先にあたります。
酩酊ぎみの春夫らの耳朶(じだ)を打ったのは、号外を告げる忙しい鈴の音でした。「号外、号外!大逆事件の逆徒判決の号外!」と、怒鳴りたてながら駆け過ぎていったということです。胸に下げたビラから、街頭の灯影でわずかに「死刑十二人無期十二人!」と読めたといいます。「僕は全身冷水を浴びせられた思いで、二人の友には号外の僕に与えたショックを説明して、彼等と遊興をともにすることを断ってひとり帰った。そうしてその夜半、僕は近く処刑されるべき大石誠之助の死を弔う一詩を草した」と、春夫は後年『わんぱく時代』のなかで述べています。
「死刑十二人無期十二人」の号外の内容は、必ずしも正しくはない。特赦は、翌19日に発表されたことなので、号外の内容は、24名の死刑判決を告げていたはずで、うち6名は同郷の熊野新宮の土地の者だったのです。また、春夫が号外で受けた衝撃を、そのまま詩にしたのは「愚者の死」とされますが、内容からみて、18、19日にすぐにできあがったものではない。すくなくとも、24日の処刑以後です。
春夫はこの時、本郷区湯島新花町54の本郷座の座方をしていた吉澤真次郎方に、新宮中学5回生の同級である東煕市(ひがしきいち)と同居していました。「愚者の死」はこの下宿でできあがったものです。
東は三重県南牟婁郡尾呂志(おろし)村出身で、医学校をめざして浪人中でした。後年の春夫文学の代表作「女誡扇綺譚(じょかいせんきたん)」などの、いわゆる「台湾もの」の成立の影の恩人と言ってもいい人物です。
新進作家として出発を始めた春夫が陥ったスランプ、台湾で歯科医を開業していた東に誘われての台湾行きをきっかけにして、春夫文学が新展開を見せたとも言えるのです(藤井省三らの研究によって、「女誡扇綺譚」などを、これまでのように「日本版オリエンタリズム」だけで解釈してはいけないという考えが浸透してきている)。
東は、尾呂志の酒屋の大富豪東家の分家筋裏地家の出で、本家の東家は、大石誠之助の大石家とも繋がりが深かったのです。誠之助の兄余平が下北山村の西村冬を嫁に迎えるとき、この地では前代未聞の豪華な行列が、この東家に1泊して、新宮を目指したのであり、後の世までの語り草になっています。冬の母もんは、実家が尾呂志の大庄屋を努めたほどの旧家でしたが、山林王西村家に嫁ぐに当たって、財産上の釣り合いから一旦酒屋東家の養女に入ってから嫁いだのです(芝﨑格尚著「尾呂志の酒屋、東家の人々」・『熊野の歴史を生きた人々』所収)。
もうひとり、近くの本郷区湯島新花町33番地下平文柳方(尾呂志村ゆかりの医学博士下平用彩の弟宅)に、やはり新宮中学の同級生川村淳一が下宿しており、停留所で電車待ちをしていたのはこの3人です。
ところで、佐藤春夫にとって大石誠之助は、父豊太郎の5歳下、1867年(慶応3)の生まれ、いわば父親の世代の人です。誠之助が刑死したのは、満43歳2ケ月でした。しかも父と同じ医師仲間で、文学面でも情歌や俳句で共通面を持っていました。豊太郎は誠之助から、幸徳秋水が訳したクロポトキンの「麺麭(パン)の略取」秘密出版本を借り受けていて、家宅捜索当時の父の狼狽振りを、春夫は幾つかの作品で描いています(「日本ところどころ」など)。中学生の春夫も、この本を読んでいたようです。幸徳秋水の翻訳本はたちまち20部が差し押さえられたようですが、2000部が全国に出回っていて、春夫が読んだのはそのうちの1冊でした。「日本語訳「麺麭の略取」は、政府によって販売禁止の処分をうけました。私の家は警官によって捜索され、すべての部数が押収されました。しかし、彼らが見つけることができたのはわずか二〇部だけでした。何と、良い政府であり、賢明な警察であることか!」という、1909年(明治42)2月4日付の幸徳秋水のクロポトキン宛ての書簡が最近発見され、話題になりました(「初期社会主義研究」30号・2022年3月)。
春夫は、誠之助らが開設していた新聞雑誌縦覧所に通い、東京で発刊される「新思想」を盛り込んだ雑誌や新聞を多く熟読しました。1909年(明治42)与謝野寛らが来訪したときなどは、講演会の場で突如登壇して波紋を広げるのですが、社会主義と文学との関係を巡って、誠之助と論争までしています。誠之助は、社会主義が実現すれば生計にゆとりができ、文学を楽しむ時代が来て、文運大いに栄えるとしたのに対し、春夫は今日と同じく、一部の文学好きばかりしか楽しまず、芸術そのものが娯楽化、平板化すると「小生意気((こなまいき)にも」食い下がった(『詩文半世紀』)ことはすでに述べた通りです。
春夫が「青春放浪」のなかで、「わたくしは大逆事件のおかげでまつしぐらに芸術に向かつた。そうしてそののちの彷徨はもつぱら芸術の部門に限られるような結果となつた」という発言のある所以です。しかし、「大逆事件」の衝撃、誠之助への思いは、戦前でも、事あるごとに春夫の脳裡に想起されたと思われます。
1927年(昭和2)雑誌「新潮」11月号に掲載された座談会「佐藤春夫氏との思想・芸術問答」のなかで、評論家大宅壮一の質問攻めに春夫は、社会主義に共鳴した青春時代があったことを、ふと漏らしています。すかさず大宅が「先生自身のさういふ気持を書いて戴きたいんです」と言うのを受けて、春夫は「書いてもいい。書きたいと思はないことはない」と応じています。そうして7年後に生まれるのが、短篇「二少年の話」や「若者」です(昭和10年刊『我が成長』所収)。後年の『わんぱく時代』の先駆けを成す作品ですが、戦前ファシズムの嵐が強まる中では大きな制約がありました。そんななか、大石ドクトルや新村忠雄が実名で登場します。
1964年(昭和39)春夫が72歳で急逝したとき、先輩格の和貝夕潮が春夫の忘れられない歌として、次の和歌を引用しています(「熊野新聞」昭和39年5月21日付)。
「十二人処刑せられし夕まぐれ千代田の宮は雪真白なり」
処刑の日の前後、東京は異例の大雪が続きました。東京監獄にも宮城にも、等し並みに雪が降り積もったのです。春夫のこの歌は、和貝の記憶に存するだけだったのです。
辻本雄一