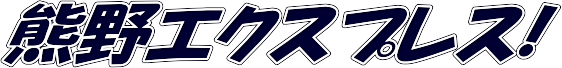イワシ漁の発展は綿にあり!
木綿が輸入から国産化に
古代から、日本人の衣服や寝具の材料は、貴族は絹、庶民は麻などであり、今日普通に使われている木綿が普及したのは、16世紀の後半になってからでした。麻などの繊維は丈夫でしたが肌触りが悪く保温力がないことが大きな欠点でした。
それに比べて木綿は柔らかで肌触りがよく、何よりも保温力が高くて冬の衣料としても暖かくて重宝されました。丈夫で水にも強く、しかも値段が割安という長所を持った繊維でした。そのため木綿の需要は革命的に急速に庶民の間に広まっていきました。
当時木綿は輸入品でしたが、需要が急増するにつれて、中国や朝鮮からの輸入だけでは供給が追いつかなくなりました。薩摩、博多などで、種を輸入して綿花を育て、国産化を目指すようになりました。さらに16世紀末には、摂津、 和泉、伊勢、尾張、三河などでも盛んに栽培されるようになりましたが、いくら作っても増え続ける需要に追いつけない状態でした。
肥料として利用された鰯
一方、古来わが国では、田畑の肥料といえば、草や落ち葉を堆肥にしたり、人や家畜の糞尿を腐らせて使っていました。しかしこれらは、窒素、燐酸、カリなどが少なくて、綿を作っても質のいいものが採れませんでした。
ここで、有機肥料として登場したのが、干鰯(ホシカ)と呼ばれた鰯を干した肥料です。干鰯は綿の苗が育ってから途中でやる追肥として使われ、綿一本に対して干鰯一匹を土の中に差し込んで肥料にしたといわれます。これを使うと、綿の実が格段に大きく育ち、収穫量も飛躍的に増えました。
当時の農村では、米作りが主でしたが、米は半分以上、多い場合は三分の二近くが領主や地主に年貢として徴収されました。そのため大方の農家では、米を売って生活するなどということは到底出来ませんでした。
16世紀の末頃の関西地方は、商業が発達し商品経済が農村にも及んできましたので、農家ではいい値段で売れて、しかも税の対象にならない作物を作る必要に迫られていました。綿の栽培は、当時の農家にとって、この上もなく有利な現金収入の道でした。ホシカを買っても、農家にとって綿栽培は十分に儲かる仕事だったのです。
関西は、特に栽培面積が多かったといわれます。新居英次氏の著書「近世の漁村」によれば、16世紀末には、これらの地方だけでも干鰯が22万5000石も必要だったといいます。そのため大阪の干鰯問屋は、漁具や漁船の費用を用意して、大阪湾や紀伊水道沿岸の漁師たちに鰯漁への出漁を奨励しました。
それらの漁民たちは、地方有力者を中心に、十数名で操る小型の地引網や八手網を小船に積んで出漁を繰り返し、イワシを大量に獲って海岸の砂浜に広げて干して、干鰯を製造しました。
さらには、水揚げしたばかりのイワシを大釜で煮て、魚油を絞り、絞り粕を浜に広げて干して〆粕も作りました。漁具を改良すれば鰯の漁獲が増える。捕っても捕っても間に合わないほど売れる。売れるから益々沢山捕る。こうして鰯を乱獲したため、関西の漁場はたちまち鰯が枯渇して不漁になってしまいました。
しかし干鰯や〆粕は木綿の糸や織物を紺色に染める藍や、照明用の油を絞る菜種を育てる肥料にしたり、更にはミカン栽培の肥料にも使われたりと、干鰯の需要は増える一方でした。
紀州を始め摂津、和泉などの漁民たちは、長い航海に耐えられ、沢山の荷を積める船を造って、四国・九州、五島列島から日本海にまで出漁するようになりました。
当時は「鰯は海から湧いてくるものだ」と思われていて、今日のような資源保護の思想はありませんでした。ですからここでもまた、幾ら捕っても売れるから捕る、捕るから漁場が荒れて捕れなくなると言う悪循環が繰り返されて、江戸時代の初め頃には、四国・九州方面の鰯漁業も行き詰まってきまし た。
最近イワシはDHAやEPAなどを多量に含む栄養食品として脚光を浴びていますが、それでも漁獲量の大部分は豚やにわとりや養殖の魚のえさに使われ、人間の食卓に乗るのは総漁獲量のわずか3%程度といわれています。
16世紀の後半に、関西で網と船をつかって大量に漁獲をする、本格的な漁業の夜明けをもたらしたのはイワシ漁でしたが、この場合もイワシは食品としてで はなく、畠の肥料として捕られたわけです。当時の日本人の食生活は大変粗食で、魚はたまにしか食べなかったようですから、農民より綿のほうがずっといい食事をしていたといえそうです。
(出典:東国漁業の夜明けと紀州海民の活躍)
八咫烏