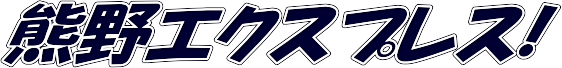「春夫詩句を拾う!!」(4)
どうぞお楽しみください。
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・
| さんま、さんま、
さんま苦(にが)いか塩(しよ)つぱいか。 そが上に熱(あつ)き涙をしたたらせて さんまを食ふはいづこの里のならひぞや。 (一九二一年一〇月「秋刀魚(さんま)の歌」・『我が一九二二年』所収) |
この作品の舞台は、神奈川県小田原の谷崎潤一郎邸。
さんまの季節は、ちょうど温州ミカンが青さを増してゆく頃。まだ酸(す)っぱさが残るみかんを、ミカン酢(ず)のように絞り出す。しかし、熊野の地のように、まだ青いミカンをもいできて使うのではなく、涙を、悲恋の涙を、蜜柑酢(みかんず)代わりにして、さんまを賞味するのは、いったいどこの土地の習性なのだろうか。自己韜晦(とうかい)した、自分を突き放した諧謔(かいぎゃく)、ユーモアの味をしみこませる。
終句は、「あはれ、/ げにそは問はまほしくをかし。」である。それは、おろかしく、こっけいなことだ。「あはれ」で始まったこの詩は、「をかし」で終わる。「あはれ」と「をかし」は、平安時代以来のわが国の情緒を表す象徴的なことばであった。