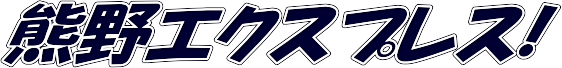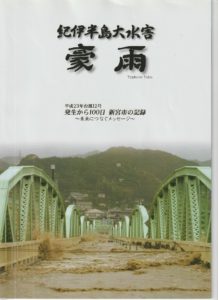館長のつぶやき〜「佐藤春夫の少年時代」70
「反骨」から「日本人ならざる者」の自覚へ
春夫が新宮中学を卒業して、7月の第1高等学校受験を目指し、受験に挑んだが挫折、与謝野寛らの勧めもあって、親交を深めつつあった堀口大学とともに、永井荷風を慕って改めて慶応義塾予科に入学するのは9月のことです。上京後の春夫の「文学生活」が始まり、「春夫の少年時代」としてこまごまと辿って来た道筋も、漸く終わりを迎えるのですが、そのまま終わりを告げられないのは、故郷熊野新宮で起こった「大逆事件」の衝撃にも触れざるを得ないからです。春夫の「反骨精神」は、さらに重層化、屈折化を強いられたと判断されるからです。熊野新宮で起こったと言うのは正しくはありません。全国を巻き込んだ事件が、新宮にも「飛び火」したと言うのが正しい。そうして、逮捕、拘禁されていった人たちは、熊野と言う土地で生活する人たちであり、春夫も日頃見知っていた人たちだったのです。幸徳秋水等と違って、東京や大阪などに出て、活躍していた人たちではない。ここでも、土地、地域がターゲットにされたという意識を、一部の識者は感じ取ったとしても不思議ではありません。東京に出た春夫の内心も穏やかには過ごせなかっただろうと思われます。
先を急ぎ過ぎましたが、若き日の春夫の「反骨精神」に戻れば、春夫から父豊太郎に宛てた400字詰5枚の書翰が残されていて、参考になります。初めて公表された「ポリタイア」3巻1号(昭和45年6月)には1912(明治45)年4月16日付とあるのですが、内容から判断して、実際には1911年(明治44)年4月、「愚者の死」発表直後とするのが正しい(すでに、浜崎美景著「森鷗外周辺」等で疑義が提出されていた)。この書簡は、若き日の春夫を知る資料が乏しいなかで、珍しくて貴重なものです。慶應大学在学中の子に、父は高等学校受験を再度要請してきたのでしょう、そのことに断固たる拒絶の態度を示した手紙です。当時は、高等学校と私立学校とでは、社会的な認識、評価の点では雲泥の差がありました。
「一、高等学校に入学せぬと云ふ事は作家は深く学ぶの要なしと云ふ事とは全然根底を異にすること也。……一、学問は高等学校の専売にあらず。……一、個人を尊重することを知らず、正しき校風の名の下に多数者の勢力を振ふこと高等学校より甚だしきはなし」と述べ、高等学校が森鷗外の小説を禁止したこと、「最近、徳富健次郎氏の意義ある演説に報ゆるに鉄拳を以てせんとせし生徒の学校なり。明治四十四年と云ふ聖代にありて然も文芸部の主催せる講演会に両三名婦人の聴衆ありしが故にその閉会後塩を撒けりと云ふ学校なり」と言い及んでゆきます。1高での徳富蘆花の「大逆事件」犠牲者擁護の演説(「謀反論」)は、さまざまな波紋を広げ物議をかもしましたが、春夫はすでに同時代に明確に「意義ある演説」と評価しています。蘆花はそこで、「諸君、幸徳君らは時の政府に謀叛人と見做されて殺された。諸君、謀叛を恐れてはならぬ。謀叛人を恐れてはならぬ。自ら謀叛人となるを恐れてはならぬ。新しいものは常に謀叛である」と語って、聴衆に多大な影響を与えたのです。なかに、芥川龍之介も混じっていたのではないかという推測が、親友の日記の発見などによって、関口安義などによって説かれています。さらに春夫は、「一、帝国大学の図書館に於てはその後一切社会主義の書物を貸さずと云ふ(附記す、鷗外博士曰く、社会主義と自然主義を外にして近代の文学なしと。)堪えがたき哉、官僚の臭、児は何所にか文学を学ぶべき」と言い、「一、要するに高等学校及び大学は文学を究めむとする児等にありて遂に何等の権威と関係とを有せざる也」と断言します。文学の道に進もうとする決意が、個の強さを際立たせています。春夫はこのとき19歳の誕生日を過ぎたばかり、これほど率直に自己表現できる背景には、多くの書物を渉猟し、「新思想」を吸収したところからくる強い個の独立を感じさせるものがあります。
書簡で春夫は、仕送り13円の使途を銘記し購入本の内訳を記したあとで、さすがに強い口調に気が咎(とが)めたのか、「初め書き出しのあたり少しく激烈に過ぎたれば差し出すことためらひ候へどもそのままにて御送り申し上げ候。立ちどころに理解下さらずばとても説得いたしがたかるべく手紙は愚か口で申し上ぐるももどかしく候、兎に角一応最後の御考を受けたまはるべきか」と、末尾近くで述べています。この書簡から窺えるのは、一見反発の底に流れている父への敬意です。春夫も書きよどんだと見えて、12日深夜に書きかけた手紙を一旦停止し、16日に仕上げていることからも分かります。
春夫の父への確執(かくしつ)と和解の歴史は、かって私は「父と子、『確執』から『和解』へのみちのりー佐藤春夫と父豊太郎にとっての『強権』」(「熊野誌」55号・平成20年12月)で詳しく述べたことがあるので、ご参照いただくとありがたく思います。その後半生で父祖伝来の下里(しもさと・現那智勝浦町)の「懸泉堂」を継ぐことになった父豊太郎は、まもなく鉄道建設のために敷地が半減され、破壊されてゆく現状を目の当たりしなければならなくなるのです。それは強引な国家権力の介入でした。一部の識者は、万葉集以来の歌枕の地「玉之浦海岸」と文人が立ち寄った由来ある「懸泉堂」を守れと言う運動を展開してくれましたが、奏功せずに、戦時下、国家権力の横暴を親子して体験する羽目になるのです。それは、「大逆事件」の追体験を想起させたのではないのか、というのが私の仮説です。
春夫は書いています。
「同じく十七、八歳のころから、これも漠然と社会主義思想のようなものに感染していた。故郷の町にそんな空気がみなぎっていたからであろう。もしわたくしが貧家の子弟であったか、もしまたかりに暴富の家の子であったならば、わたくしはもっと本気に社会主義者になっていたであろうが、わたくしはただ理論的にこれに共鳴しただけで骨身にしみてこれを信奉しないでしまった。そうして大逆事件がわたくしから社会主義を撲滅した。わたくしは何やらもっとほかに一命をささげるべきものがあるような気がしたためであった。それにしてももし大逆事件がなかったとしたら、社会主義はもっと根強くわたくしの心中において育って行ったものであったに違いない。/わたくしは大逆事件のおかげでまっしぐらに芸術に向かった。そうしてそののちの彷徨はもっぱら芸術の部門に限られるような結果になった。」(「青春放浪」・昭和37年4~5月読売新聞夕刊)
慶応義塾の師であった永井荷風も、「大逆事件」から大きな衝撃を受けたひとりでした。被告達の囚人馬車を市ヶ谷の通りで目の当たりにして、何事も成し得ない自責の念に駆られ、フランスの作家エミール・ゾラが「ドレフュス事件」のドレフュス大尉の無実に対して敢然と戦った論陣のひとかけらも発言にし得ない自分を、「以来わたしは自分の芸術の品位を江戸戯作者のなした程度まで引下げるに如(し)くはないと思案した」と宣言せざるをえなかったのです(「花火」大正8年12月)。しかしながら、韜晦(とうかい)の意味が込められているとはいえ、それは、春夫の論理からすれば、国家に囲い込まれている第1高等学校内からは到底出てこない発言だったはずです。
辻本雄一