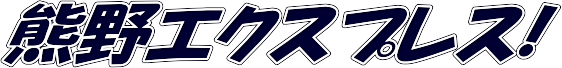館長のつぶやき〜「佐藤春夫の少年時代」65
 生田春月との関係(二)
生田春月との関係(二)
春月は、大正3年以来、亡くなる昭和5年までの足かけ16年間を、弁天町・天神町など東京の牛込の地で過ごしました。詩作のかたわら独逸語専修学校の夜学でドイツ語を学んだ春月は、ハイネなどドイツ文学を紹介したり、ツルゲーネフ、ゴーリキーらの作品を翻訳したりもしました。大正6年、天神町在住時には第1詩集「霊魂の秋」を発表、翌年この地で発表した第2詩集「感傷の春」によって詩人としての地位を確立しました。その後も「春月小曲集」「慰めの国」「夢心地」「自然の恵み」などの詩集や、自伝的長編小説「相寄る魂」、評論「真実に生きる悩み」「山家文学論集」など、すべては牛込の地で著されたのです。その周辺には、春夫が住み、奥栄一が住んでいました。
そうして春月は、昭和5年5月19日に大阪商船すみれ丸に便乗、別府に向かう途中の瀬戸内の播磨灘に身を投じて自殺したのでした。
昭和5年7月刊の「文学時代」には、「生田春月追悼録」特集が組まれており、自殺直前の長編詩「愚かな白鳥」や「新しい歌、より善い歌」が収められ、6人の知人、友人達が、詩や文章で追悼しています。佐藤春夫は「流水歌」という詩を、奥栄一は「生田春月の思ひ出」を書いています。
『文学時代』 昭和5年7月 新潮社刊
5月25日に多聞院(東京・新宿弁天町)で告別式が営まれ、春夫も参列していて、一同撮影の写真が、同雑誌の口絵に紹介されています。また、その前日、日比谷の山水楼で作家龍膽寺雄の「アパート女達と僕と」の出版記念会が開かれ、そこにも春夫は出席、記念撮影した写真が同誌の次の頁に出ています。
奥栄一の追悼文は「その思ひ出の中の断想」とサブタイトルが付されているように、折に触れての春月との係わりを、個人的な感慨を含めて叙述したものです。
「蒼白く、細長い、その頤の突んがつた彼の顔は、彼自身も心ひそかに少年らしい矜持をもつて認めてゐたやうに、ハインリツヒ・ハイネのそれによく似てゐた。」で書きだされています。春月を知ったのは明治43年春、初めて東京に出て来て間もなくの頃、名前はそれ以前に「文章世界」の投書を通して関心を持っていました。「彼はその極めて口数の尠い言葉を話すと云ふよりは呟く、独言のやうに口の中で私語いた。私は当時既に彼の友達であり、私の子供の時分の友達である佐藤春夫の通弁で、やつと彼と話す事が出来たのを憶えてゐる。」と言います。以来、20年の付き合いが始まったようです。
「彼にはとても常人では想像出来ない、いこぢな、さうして、どんな苦しい時でも、ぢつと自分だけで我慢してゐる強さが、その多感な内気な半面に一貫してゐた。」とも言います。
「三日にあげず訪れて行」ったという奥は、春月の詩作や翻訳に打ち込むノーマルな精進生活とともに、周期ともいうべき爆発的なアブノーマルな奇行の姿も捉えています。「新しい女」と標榜された雑誌「青鞜」に寄稿した文章を読んで、すぐに求婚して妻に迎えた花世とのエピソードも紹介。ふたりとも社会問題や女性問題に関心を持つ妻を迎え、極貧の生活を強いられたという相似た境遇が、当初の春月と春夫との親密度よりも、いっそう奥との親密度がより増していったようにも見えます。ふたりはアナーキズムについてもよく語り合ったと言いますが、一言で「無政府主義」と片づけられることも多いのですが、社会連帯や団結とも結びつく要素もあって、奥に言わせれば、春月のアナーキズムは「インデイヴイデユアル・アナキズム」であったといいますから、実践に結びつくものではなかったのです。その拠ってくるニヒリズムも「彼が好む処の逆説(パラドツクス)を以て云へば、彼自らの野心を、彼自らの感情的な、余りに多感な性情を否定する為めの、意識せざる保護色ではなかつたか。」と踏み込んだ鋭い分析をしています。そして聞くところによれば、として、数日後故郷でやることになっていた講演の題が「知識階級の行衛」であったことを明かしています。
春夫は春月との微妙な関係にも触れ、近頃は疎遠になっていたとも言いますが、「流水歌―生田春月を弔ふ」の詩を捧げています。
「君とわれとは過ぎし日の / 歌と酒との友なりき / 眉わかくしてもろともに / 十年かはらぬ朝夕を / われらは何を語りしか」で始まり、「人に驕れるわが性(さが)は / 君が怒を得にけらし」と、ふたりはしばらく疎遠になり、己が道を歩み始めていたと言います。
「かくて十年また過ぎぬ / 眠なき夜のをりふしに / 生き來し方を見かへれば / 少年の友よき宝 / またと有るべきものならじ」と、初めて出会った少年時代を懐かしみます。そうして、いよいよ永別の大団円、「よき折あらば手をとりて / 杯くまん日もがなと / 思ふねがひはあだにして / 君今は世にあらざるか。// 歌うづ高く世にのこし / むくろは水にゆだねつつ / 騒愁の人いまは亡(な)し / ああ若き日の友は亡し / 愛も憎もすて去りし / 仏の前に額づけば / 七情の巣のうつそ身の / わが目や水は流れけり / 君葬りしその水は。」と結ばれています。
汽船に乗り込む直前まで、大阪のホテルの一室で長編詩完成のためにペンを走らせ、活字の組み方やポイントの大きさ、行間アキの指示まで書き込んで投函したという春月の遺作詩が「愚かな白鳥」でした。女性問題の悩みを抱えている様子が窺えることばの数々からは、虚無の翳りがほとばしり出ています。そうして「一生は稲妻、 / まぼろしを人はとらへて / 詩はここに、死もここに。」の詩句もあって、死の予兆も顕著です。
僕が死んだら誄(るい)を述べる(弔辞を述べるの意)のは君だ、と春夫に言い残して、芥川龍之介が自裁したのは、昭和2年7月24日のことでした。春夫はそれを、中国・上海の宿で知るのです。龍之介の残したことばー「ぼんやりした不安」は、昭和恐慌(きょうこう)と言う不況が襲ってくる世相の中で、先行きの不透明を象徴する流行語になっていきました。それから3年、春夫が例の細君譲渡事件で世間をにぎわわせ、千代との10年来の恋を実現させるのは、春月の自殺から数ケ月後の8月のことであったのです。
辻本雄一