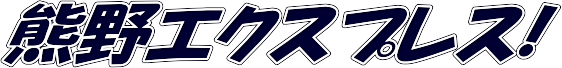館長のつぶやき〜「佐藤春夫の少年時代」55
春夫、生田長江に同行 (一)
春夫は後年、生田長江との出会いについて、次のように語っています(「文芸」昭和31年5月「対談・現代文学史=スバル時代=」)。
ああ、それでね、その講演会の時に長江先生とぼくは肝胆相照らした、という感じです。長江先生の意見にぼくは非常に共感を感じて、それからあとの座談会の時に、大石誠之助と、「社会主義と芸術」というような問題で話合つたんです。大石は、社会主義の世の中になると、みんな金持ちになる、そうすると生活が楽になるから、誰も彼も芸術家になる、というような公式論を述べた。
ぼくはそれに対して、そういう一面もあるだらうけれども、みんな金持ちになれば、社会現象が単純になつて、逆に小説のテーマとして面白くなくなるから、必ずしもいい面ばかり考えられない。生活がゆたかになることは疑わないとしても、必ずしも芸術の方面はトクでもない、というような話を、だいぶ、しばらく、してましたよ。長江先生、途中で冷かしたり、いろいろなことをしていてね、あとで「あの時の君の話は面白かつた」と、そう言つてくれたんです。まあ、そういうことで、この小僧、なかなかおもしろいと思つたらしい。それからぼくが京都へいく用があつてね・・・・(ママ)」
春夫と大石誠之助との論争は、「詩文半世紀」にも語られていますが、春夫の「社会主義」への対応を考える上では注目されます。大石はまた、石井柏亭とも、装幀の問題をめぐって論争をしたらしい(「柏亭自伝」)。
この頃の大石誠之助
春夫は後年の回想で(「先師を憶ふ」・昭和33年6月「現代日本文学全集」の長江に関する解説)、大石との論争をさらに詳しく記述してくれています。「その歓迎の茶話会の席上で、偶(たまたま)同じく出席してゐた禄亭大石誠之助(後年の大逆事件で刑死した一人である)が社会主義社会での文学の興隆を説いたのに対して、僕は子供らしい疑義を発してその質問がやがてつづいて駁論になり、論戦ともなく食い下つて行く僕の云ひ分を黙つて笑ひながら耳を傾けてゐてくれた先師は僕の云はうとするところを察して補足してくれたり、また禄亭の意見を僕のために諄諄と説き直してくれたりしてゐたが、やがて相方の云ひ分の尽きたところで行司役を買つて出て、それぞれに分相応の体面を保たせながら議論を引き分けにしてくれたものであつた。僕はその時以来、長江先生の知遇を得たやうにうぬぼれてゐる。」と。
春夫は生田長江が「学術大演説会」の当日、「最近の文壇を論ず」を弁じたように語っていますが、実際の演題は「ハイカラの精神を論ず」で、22日からの連続夏期講演会では「近代文芸としての自然主義」を論じています。これらの内容は、若き新進の批評家として、西欧文学への造詣の深さなど、地方の知識人たちにも、斬新な覚醒を促すものではなかったか。
春夫は後年回想して(前出の後年回想)、「自然主義小説一般から、花袋、藤村、そうして当時売り出したばかりの白鳥の作風や作品を論評した。白皙(はくせき)な顔にいかめしい髭(写真で見おぼえてゐる鷗外のものに髣髴(ほうふつ)たる)をひねり上げたこの若い文学士は爽快無比な口調で論じ来り論じ去つて人を倦(う)ましめないばかりか甚しく魅力のあるーといふのは面白い表現やザツクバランな口調に警句などを頻発する間にも学問的なものを適当に加味した、面白く内容のある、さうして多くの人々にも親しまれ理解されるやうなこの弁士の雄弁は場を圧したものであつた。」と述べています。長江が「理想としての自然主義」を鼓吹し、近時の文芸界に西欧との同時代性を視ようとしているのなどは、若い春夫などにも多大な影響を与えるものだったはずです。
生田長江は明治40年10月「文学入門」を夏目漱石の序文を付して刊行し、春夫も愛読しましたが、この小冊子は「今回想するところでは極く簡単な文学概論のほかに文学者たらんとする青少年に必読の古典や内外の名著の目録を選んで解説やその必読書たる理由などを説いてゐたものであつたやうにおぼえてゐる。」(前出の後年回想)と語っていっています。
更に、明治41年9月には「外国文学研究法」を刊行して、世界の文学状況を知る格好の手引書として、読書界では広く迎えられました。春夫も長江に心酔する形で、以後、行動を共にすることになるのです。