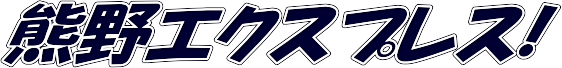館長のつぶやき~「佐藤春夫の少年時代」(47)
下村悦夫と富ノ澤麟太郎(一)
もう少し大正13年の徐福墓畔と春夫らの文学仲間の存在を追ってみます。
人家が増え、新開地になるにつれて、徐福の墓の境内は一時わずかに30坪ほどになったといいますが、大正5年に熊野地青年会の幹部が境内を修築、「七塚の碑」も建立され、境内の周囲が整備されました。翌6年保田宗次郎が隣接地を寄付、大正14年熊野地青年会の幹部を中心に徐福保存会が設立され、400余円を募金、隣接地百坪余を買収、境内を拡張していきました。翌15年徐福保存会とは別に徐福信徒の人達が徐福講を組織、9月1日を八朔(はっさく)の日(旧暦の8月1日。お盆の盂蘭盆の最後の日にあたる)と定め供養の祭りを始めます。現在も使われている徐福の御詠歌はこの時作られたものと言います。
ところで、春夫の熊野への帰省滞在が、1年ほどに及んだのは、そうして神経衰弱に悩ませられたのは、ひとつに新進気鋭で将来を嘱望された作家富ノ澤麟太郎が熊野の地で僅か満25歳で急逝したことと関連があります。
富ノ澤麟太郎が春夫の下に出入りするようになったのは、熊野出身の詩人中井繁一を介してで、大正8年2月のことです(大正15年「現代小説全集」の春夫自筆による。春夫全集の年譜で12月とあるのは誤り)。麟太郎は、早大の同級生横光利一や中山義秀らと同人雑誌「街」や「塔」と係わり、作品を発表していました。麟太郎は、春夫の推薦で当時有力な雑誌「改造」に「流星」を発表(大正13年10月号)、新進作家として注目され始めていました。次回作を書き悩んでいる麟太郎を見かねて、帰省予定の春夫は熊野へ誘い、そこでの創作活動を勧めるのです。
富ノ澤麟太郎
麟太郎を春夫に紹介した中井繁一は、「さめらう(醒郎)」とも号して、春夫より2歳年下、三重県五郷村湯屋(いさとむらゆや・現熊野市)の出身、ローマ字運動に参加、社会運動にも関心が高く、大正5年熊野で「KUMANO―KAIDOO」というローマ字の口語詩集を上梓、わが国初のローマ字詩集の地位を得ますが、それが仙台の中学で学んでいた麟太郎の目に留まり、以後文通が始まり、上京後さらに交流が深まったようです。
大正15年8月中井繁一は「ゼリビンズの函」という詩集を刊行していますが、春夫は「「ゼリビンズの函」の著者」という序文を寄せています。―「この詩集の著者は、予の弟が少年時代からの友人である。/ 彼は自然に恵まれた熊野川上流の地に育つた。郵便局に勤めてゐたが、ローマ字運動に驚異的の感興を起した。彼が今日、上京してゐる最初の動機は多分これだらうと思ふ。/ 彼は貧困のなかでよく詩を愛した。ドイツ製の封筒と書翰用箋とを持つて、近郊から市中へ行商に来る時、彼が携へたものは一個の大きな握飯と林檎とであつた。全く詩的な弁当ではないか。/ 彼は後に職業を転じて、今はさるささやかな印刷屋の主(あるじ)である。
略)」と。跋文は鳴海要吉、装幀は武井武雄です。武井は「童画」の命名者で、デザインや装幀の分野でも新機軸を出し、その後春夫とコラボした作品も残しています。版元の恵風館は、東京・芝区白金の「鈴木恵一」となっていますが、中井が立ち上げた印刷屋との関係は詳らかではありません。ゼリビンズとは、小さな豆の形にして乾燥させたゼリーに糖衣をかけ、蜜蠟(みつろう)でつやを出したキャンディー。麟太郎の「流星」の中にも、「赤や白のゼリビンズ」という表記があります。
中井は春夫の弟秋雄とも交流があり、さらに富ノ澤麟太郎などと拡がってゆきます。麟太郎が熊野への誘いに乗ったのも、こういった交流とも係わっっているのでしょうか。
しかしながら麟太郎は、熊野に到着まもなく、ワイル病という感染症で病臥の身となり、2月に入って母親がひとり息子のために看病に熊野にやってきます。その2週間後、急性の心臓麻痺が原因で帰らぬ人となりました。大正14年2月24日のことです。
臨終の場に立ち合ったのは、医療処置を行った春夫の父豊太郎、春夫、麟太郎の母、それに改造社の編集者宮城久輝らです。宮城は「春宵焼友」(しゅんしょうしょうゆう)という哀切極まりない文語調の文章で、麟太郎の荼毘の様子を伝えています(「文芸時代」5月号の富ノ澤追悼特集)。それは、懸泉堂近くの万葉集以来の歌枕の地玉之浦海岸です。息を引き取る間際の様子は、次のように記されています。
「佐藤氏は、夕方より注射や酸素吸入に一心をこらす氏の尊父が、君の枕頭近く酸素吸入をし給ふ下より手を差出せしに、君も先生の手を握りて、「先生、お世話になりました。お母さんををよろしく」と言つた。/ 信ずる者に厚き佐藤氏のその時の哀惜の情は、只だその場にありし人々のみ、よく知るであらう。」
遺骨を抱いて憔悴しきって帰京した母親は、息子の急死をめぐって、春夫家族の対応に不満を漏らしたことなどから、麟太郎の親友の横光利一が春夫への不信を吐露(「富ノ澤麟太郎の死」・大正14年3月5日付読売新聞)、母の言を鵜吞みにした横光、さらには、ライバル誌「改造」に肩入れする春夫を快く思っていなかった「文藝春秋」誌が、「佐藤春夫、富ノ澤麟太郎の死に冷酷」というゴシップまがいの記事を流したりしたことなどから、春夫は思わぬ渦に書き込まれてしまうのです。そのことが、春夫の神経衰弱を増進させ、上京の機会をより遅くさせてしまったようです。そんな苦境を察してか、芥川龍之介が慰めの言葉をかけてくれた思い出を春夫は、「改造」昭和3年7月号の「芥川龍之介を憶ふ」の文章で述べています。この時芥川はすでに亡く、自裁した後のことです。