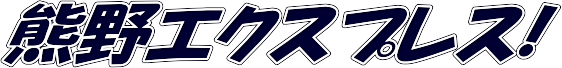田辺と新宮の市民文化
風土的特徴
田辺と新宮とは、紀伊半島の西側と東側に位置し、距離にして約120キロ離れている。いずれも紀州藩付家老の安藤氏と水野氏が治めた城下町で、幕末の文化状況を引き継いで、近代に入っても独特な文化土壌を育んできたといえる。もともと、牟婁郡と総称される地域が、ひとつの文化圏を形成していたといえるが、明治新政府は熊野川を県境に、今の和歌山県・三重県を作り上げた。
田辺は、上方に近く藩の内政に関与した安藤氏が領していたのに対して、新宮は水野氏が江戸詰めということもあり、木材の流通などを通じて江戸との結びつきを深め、江戸文化の影響を受け、堅実な商業の田辺に対して、派手な一面を覗かせていた。
幕末の紀州藩全体は文化水準も高く、田辺は比較的その影響下にあったが、新宮が江戸文化の影響を直接受ける形になったのは、九代領主水野忠央が失脚し新宮への蟄居を命じられたとき、お抱えの文化人を多く新宮にともなったことも影響していよう。新宮では、幕末から明治期にかけて、情歌(都都逸)や端歌などが一般庶民にまで流行していたという。
雑誌などの刊行
田辺では、明治十年代後半に盛んになった自由民権運動の影響下に「熊野叢誌」「田辺近報」や「幼年雑誌」の投稿雑誌が刊行されていたことが確認できる。やがて、明治三十三年(1900)に、「牟婁新報」が発刊され、一時は社会主義系の新聞として全国的にも注目され、田辺在住の南方熊楠が神社合祀反対の論陣を張ったりした。
新宮では、やはり投稿雑誌として若林欽堂によって1895年「菁莪」が刊行され、1905年には新派俳句を中心とした「はまゆふ」が発刊されている。さらに復刊号が短歌を中心として発刊され、わずか2号で終わっているが、佐藤春夫の文学的な出発を告げる雑誌になった。
大正時代はしばらくは「大逆事件」の影響で、自由に雑誌を刊行する雰囲気は失われたが、大正デモクラシーが浸透するなかで、田辺では、大正13年(1924)福本鯨洋らにより俳誌「蜜柑樹」が、新宮では、1935年平松いとどらにより、俳誌「熊野」、1923年和貝夕潮らにより短歌系雑誌「朱光土」などが刊行された。
美術界では、1913年夏、新宮で石井柏亭滞欧作品展が、西村伊作の縁で開かれているが、県内最初の洋画個展である。昭和初期、田辺で原勝四郎らを中心に「無名社」が結成され、展覧会が開かれ、新宮でも「全熊野美術協会」が結成され、展覧会が開かれている(1933年)。
(南紀と熊野古道より)