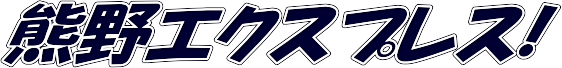かつお節考①ルーツは熊野だった!
「鰹~かつお」と聞くと、世のグルメ諸氏は、「土佐の一本釣り」や、「枕崎の鰹節加工工場」のことを思い浮かべるに違いない。そして、いつの頃からか続いているグルメブームには必ず取り上げられる調味料としての「かつおぶし」は、今や和食とともに世界的に注目を浴びはじめている。さて、この「かつおぶし」、一体だれが発明し、どのようにして広まったのでしょうか?
昔の日本では、海辺に住む人々をのぞき、魚を生で食べることはまずなく、ごく一般に干物にして食べていた。ご多分にもれず、鰹も干物にされていたのだ。この魚肉は干せば堅くなるため、古くは堅魚(かたうお)と呼ばれ、これがやがてカツオという音に変化した。後世、生の魚を鰹と言い、干したものを鰹干し(鰹節)と呼び分けたが、昔は二義が一語で済まされていて、カツオと言っただけですでに干したものを指した。
言葉が「鰹干し」から「鰹節」に変化する江戸時代の初期を過ぎた頃には、より工夫されて複雑な加工をされた商品としての鰹節ができあがっている。この考案と完成は、紀州熊野の地で行われた。ともかくも、日本の漁法の多くは古来、紀州で発明されてきたといわれる。鰹節もそのひとつであり、さらにその製法を広めたのも紀州人によってであった。
そういえば、魚は鰹かどうかはいざ知らず、その昔、紀州熊野人たちが黒潮に乗って房総半島に行き漁法を教えた。そして、故郷を懐かしく思って付けた地名が「勝浦」や「白浜」で、今もその名が残っている。
さて、鰹節の名に値する良質の品物ができるようになったのは、江戸初期、「燻乾法」という製法が紀州熊野の地で開発されて以来であった。紀州熊野の鰹干しは木のようにかたいと、当時、評判になった。それまでの鰹干し(荒節)は副食物とみなされていた。燻乾法によって木のように固くなってから、初めて純粋に調味料として使われるようになった。
鰹漁と鰹節について考えてみるときに、この漁の技術が紀州熊野でとくに発達したのは、山が海にせまって耕地が少ないという地理的条件がまずあっただろう。この土地では、古来、田畑持ちの農民が鰹の季節だけ鰹漁をするという形態が多かったらしい。
鰹の魚群のことを群来(くき)というが、群来は黒潮に乗ってやってくる。群来は初夏から秋まで続くが、漁夫たちはその魚群のなかに船を乗り入れる。鰯などの生餌をまいて魚群を水面にひきよせている間に大量に竿釣りする。短時間勝負の漁法だ。
初夏、青葉の頃、一番にとれた鰹はいわゆる初鰹として縁起物となり需要が高く、とくに江戸では一尾3両に売れたこともあったという。獲れた鰹をすぐさま浜に持ち帰り鰹節という手の込んだ加工品に仕立てあげれば良い値で売れるのだ。
鰹の群れは、黒潮暖流の水温が上昇してくるにつれ台湾、琉球から北へのぼり、晩春には薩摩沖に達する。やがて土佐沖を通り、熊野灘を過ぎ、尾張、伊豆という沖合を経て夏には仙台沖に現れる。晩秋には三陸沖に到ってそのあたりから群游を解き分散して南へ戻っていく。
熊野では、次第に漁船の数が多くなり、地場の熊野灘だけでは漁獲が少なくなったため、冒険的な漁民たちが新しい漁場を求めて遠くへ乗り出すようになった。この勇敢さは熊野人の特徴ともいえるもので、はるかに後世、明治・大正期にこの土地の人々が南半球の豪州沿岸まで真珠貝を採りに行ったことと無縁ではないと思われる。
この気質に技術が加わっていた。当時、遠出の漁業を「沖乗り」と言ったが、西牟婁郡田並浦の伝承によると、大坂湾沿岸の和泉・岸和田の漁師がやってきて「沖乗り」のための漁船の構造を伝えたといわれている。豊臣期と思われるが、詳しいことはわかっていない。
熊野衆が、この沖乗技術をもって遠出しはじめるのは、関ヶ原の戦い前後かと思われる。かれらは、黒潮洗う土佐沖や薩摩沖まで出漁した。その沖乗漁船は25人乗りという立派な渡海船だったという。「日本水産史」の記録によると、紀州日高郡の鰹船が、元和年間(1615~1623)に、土佐の西の幡多郡の沖にあらわれている。
彼らは、陸地に鰹節の製造所としての基地を設けたかった。今日、鰹節の大きな生産地の一つである薩摩の枕崎に対しては、寛永年間(1624~1643)に、紀州の森弥兵衛という者がやってきて伝授したとわれている。土佐に対しては、その少しあとの延宝二年(1674)、紀州から通漁(かよいりょう)で土佐沖にやってくる甚太郎という者が「鰹節のおもしろい造り方を教えちゃる」と言って乾燻法を伝授したのがはじめてであるという。この伝承については植田穂氏に「改良土佐節の研究」という詳細な研究がある。
紀州熊野人は先進的であった。かれらは小さな漁船を漕いで西へ東へと出ていった。西は土佐や薩摩、あるいは五島へ、東は伊豆へと進出し、鰹節の乾燻法を教えた。教えたのは親切というよりも、獲れた鰹をすぐ陸へあげて釜にほうりこみたいからであった。ところが、鰹節生産にかけては「教え子」の方が成長した。
特に、土佐の成長には目を見張るものがあった。鰹節に目をつけた土佐藩は、この製造をほとんど準藩営ともいうべきものにした。「御用節」と名付け、各浜ごとに春秋それぞれ6百本とか8百本というふうに強制割り当てして買い上げた。その代金も市価の半額ぐらいで、貢物のようにして巻きあげたために、浜の者でも鰹節を自家用にできなかった。
藩では、節改所という役所を設け、不良品はこの役所によって刎ねられるようになった。土佐藩の物産を扱う大坂蔵屋敷は現在の西区西長堀にあった。ここに、「鰹座」という独占の同業組合があり、その「株」を持つ七軒の御用問屋がさらに品質をやかましくいった。今でもこのあたりに鰹座橋という橋があり、往年の商業機構の名残りをとどめている。
こういう藩の体制によって、土佐の浜は困窮してしまっていたが、品質だけは上がり、評判も市場占有率も本家の熊野節を凌駕するようになった。ただ、紀州熊野人は製造の本家だけに、土佐沖でも薩摩沖でも、あるいは伊豆沖でも「わしらは紀州の鰹船よ」というだけでまかり通り、たいていの漁場において入会権をもっていた。
ここに改めて、400年も前の紀州熊野の先人たちの持っていた技術と、勇敢にも故郷から新しい外の世界に打って出ようとしたその進取の気概に敬意を表したいと思う。
————————
かつおぶしアンケート
あなたは、かつおぶしのルーツが熊野であったことを知ってましたか?
アンケートにご協力ください。
西 敏