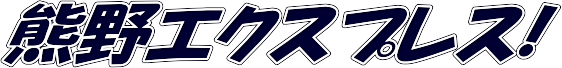笑説ハイムのひろば17 文芸館誕生
文芸館誕生

美術館のまずまずの結果に気をよくしたつくり隊スタッフは、次の企画について話し合った。”美術工芸”が済んだなら、次は”文芸”でどうだろうという意見がでた。はて、文芸と言うと、詩、小説、随筆、短歌、俳句など種々あるが、果たして掲載を希望する人がどれくらいいるだろうか。できるだけ多くの参加者を集めたいものだ。そこで、まずは、スタッフの中にモノを書いたことがある人がないか調べることにした。
恰好な人物が見つかった。つくり隊設立当時の理事会メンバーの一人で、山名と同じく広報担当理事を務めていた斉田英樹だ。聞くと、過去、ある雑誌にエッセイを連載していたことがあるとのことだ。とにかく一度読んでみたいとその雑誌を借りて、スタッフ数人が読んでみることになった。西野は、最初の一編を読んだだけで感心してしまい、斉田の書く文章が大好きになってしまった。他のスタッフも口々に、「素晴らしい」と絶賛し、これなら申し分ないと即採用が決まった。
どこが素晴らしいかというと、まず、文章が簡潔ですっきりとして読みやすい。それでいて、表現したい要点はしっかりと著されている。余計な飾り言葉がなく内容がすんなりと腑に落ちる。言ってみれば、腕の良い植木職人に剪定してもらった松の古木のようだ。西野などは、いつも余分な修飾語をつけ過ぎて回りくどい表現になってしまい反省しきりなのだ。もうひとつは、興味を持った人物のことを書いた本を読むだけではなく、その人物に所縁の地へわざわざ足を運んでいることだ。
例えば、太宰治の場合、生まれ育った青森県の実家や入水自殺をした玉川上水の現場にまで行き、そこで太宰が何を考えていたのかに思いを馳せるといった具合だ。野口英世の場合は、アメリカでの研究の現場を訪問したと思ったら、何と、アフリカにまで足を延ばして、英世の最後の地となったアクラを訪問している。これはもう、ただのアマチュアがすることではないと思い掲載された雑誌をよく見ると、そこには、「エッセイスト 斉田英樹」と書かれてあった。一定の期間連載するくらいのボリュームはあるとのことなので、スタート時点での柱になりそうだ。
「文芸」という言葉にこだわり過ぎてハードルを上げたくない。掲載を希望する者が出にくくなることのないように気をつけて、できるだけ多くの人に参加してもらいたい。何も文芸賞を狙うほどのものを要求しているわけではない。学生の時に誰でも書いたことのある読後感想文や、日々の出来事を簡単に綴ったものまで受け付けたい。小学生の文集や幼稚園児の絵日記も大歓迎だ。ただ、”文芸館”と名付ける以上、その名に恥じないものも少しは欲しい。その意味では柱になり得るものが最初から見つかったのはこの上ないことだった。
美術館の場合は、始める前から、誰々さんは水彩画や油絵を描いているとか、工芸をやっているとかの情報が既にあり、出展をお願いすべき相手が分かっていたこともあって、素早く準備行動に移れた。ところが、文芸館の場合はそうはいかなかった。ポスターを作り、掲示板に募集広告を出すことは決めたが、それほど簡単に応募があるとは思えない。そこで、つくり隊スタッフの中で過去に書いたものがあればそれをまず掲載して、呼び水にしようということになった。
西野は、もう20年も前になるが、自分のウェブサイトに掲載したイギリスの「コッツウォルズ旅行記」があったので、取りあえずそれを連載することにした。山名には、彼が福沢諭吉研究会というクラブに所属しており、その会で発表した記事があったのでそれを使うことにした。あと、鏡はフランスに宮下はオランダに仕事で駐在していたことがあったので、その当時の思い出や現地の文化などについて書いてもらうことにした。こうして、先ずは、スタッフのうちの5名の作品を掲載することでスタートした。
美術館の作品集めの時は、準備期間をじっくりかけて30名以上の出展者を集めて一斉に公開という運びになったが、文芸館は、執筆者がなかなか集まらず、ゆっくりとした船出となった。2週間、掲示板にポースターを掲げたが自ら応募してきた者はいなかった。ネットで公開することを問題視したのか、それとも、文芸館に掲載することに価値を見出してもらえなかったのか、いずれにせよ船出は順調とは言えなかった。
ものを書くという行為は、自分が思うことを言葉にしてそれを書き記すということだ。一旦書いたものは、他人の目に触れることがあるわけで、それを一生自分の手元に置いて誰にも見せないということが成りたつものなのだろうか。例えば日記は、自分のために書くもので他人に見せるものではないというのが一般的な解釈かもしれない。自分の日々の考えや行為を書き留めておき、後になってそれを見返すことが多い。その時見返しているのは、もう一人の自分であって、書いた時の自分ではない。それは他人と同じなのではないか。
とすると、書くという行為は、元々他人に見せるために書いているのではないか、そして自分自身の内面を晒すということにも繋がっているとも言える。そうであれば、書いたことのある人は、どこかで掲載されることを期待しており、反対する理由はないのではないか。唯一、掲載する価値のない媒体であると判断した場合を除いて。西野の頭の中には、さまざまな考えが浮かんでは消えていき、この文芸館をもっと盛り上げて賑やかにするにはどうすればよいのかを考えてみた。
その結果ひとつ思いついたのは、ゲスト投稿者を採用することだった。スタッフの友人・知人の中から書くことの得意な人物を選び投稿を依頼してみたところ、同意してくれた人がいた。一人は、西野の友人で詩を書いている女性だ。既に何冊かの本を出版しており、その意味ではプロであるが、西野の同級生ということで協力してくれたのだ。もう一人は、元商社マンで現在もインドに在住している人物で、こちらは山名の元同僚であった。健筆な人でこれまでに書きためた海外のエピソードは無尽蔵にあるという。
詩の方は、さすがにプロの作品ということもあり、難しくてわからないという人も多かったが、文芸館の品格を上げたのは間違いがない。そして、詩というものは、読むほうも少しかしこまって読むことになるのかも知れない。その点、ちょっとしたエピソードなどは、気楽に読めて構える必要がない。インド駐在エピソードの方は、見知らぬ土地での思いもよらない話の数々が面白いと人気が出るのはある程度予想できた。
当初、同一人物の作品を週に二回掲載してスタートしたが、ゲスト投稿者が加わったことで、週一回の掲載とすることになった。こうなると1週間、毎日別の人物の作品を読むことが出来るのでバラエティに富み変化が出るようになった。続き物は、毎日続けて読みたいと思う人もいるかもしれないが、この文芸館はネット上に展開する特殊なものであり、多くの人を相手にしていることから、まずは、最大公約数を取ることにならざるを得ない。
取りあえず、この方式で進めていき、閲覧者やスタッフの感想を踏まえて何らかの修正が必要となればその時点で検討すればよいと考えた。毎日新しい記事を掲載していいながら、一度掲載された記事は、アーカイブとして保管されているので、一つの連載記事だけをまとめて読みたいときは、作者名か、記事タイトルをクリックすれば、目的の記事一覧が現れ、連続して読むこともできるようにしてある。このことは、忙しくて毎日アクセスできない人にも有効な方法で、実際、喜ばれている。
こうして、文芸館は今も継続中であるが、実は、この文芸館が始まった2018年11月の1か月間の「ハイムのひろば」の閲覧数が、3050PV(1日平均102PV)を記録し、すべての月を上回っている。以後、1年以上経過したが未だこの記録は破られていない。いかにすればこの記録を破ることが出来るかと、西野は、密かに考えをめぐらしている。
~つづく~
蓬城 新